第九話 碧海の彼方(12)
その頃、それら炎と硝煙に霞む海域を遠くに見晴るかす洋上の小さな岩礁の上に、一人のインカ族の若い娘の姿があった。
彼女は、掲げていた望遠鏡を素早く下ろした。
短い黒髪に巻いた緋色のバンダナとスラリとした褐色の肢体が、紺碧の海に映えている。
暫し鋭い横顔を海戦の行われている洋上へと向けていたが、自分の傍で同様の方角に向けた望遠鏡を覗き込んでいるインカ兵の姿に気付くと、パシッと、相手の頭をはたいた。
兵は咄嗟に頭を押さえる。
「――てっ!」
「ちょっと!
そんなに長々と覗き込んでたら、バレるでしょっ!!
望遠鏡のそのガラスの表面、日光を思いっきり反射してんだから。
目ざとい人間が見たら、向こうからでも、私たちがここにいること一目瞭然よ」
「すっ、すいません!!」
「それより、ホラ!
はやいとこ伝令鳥、呼んで。
急いでトゥパク・アマル様に戦況をご報告しとかなきゃ」
「はっ、マルセラ様!!」

この女性――マルセラは、インカ軍の総指揮官トゥパク・アマルの重臣ビルカパサの姪にあたるが、そうした血筋や男勝りの性格もあって、今ではインカ兵たちを率いるいっぱしの連隊長の一人である。
そして、そんな彼女の部隊は、トゥパク・アマルの指示の元、ペルー沖沿岸の随所に点在する無人島や岩礁に渡って散開し、それぞれの場所から戦況を観察して陣営本部に報告する任務を遂行していた。
スペイン軍が、英国艦隊との戦端を開くであろう海域を事前に予測していたように、インカ軍もまた、その概ねの海域を予測していたのだった。
とはいえ、小島や岩礁がそう多くあるわけもなく、ましてや、その近くで都合良く海戦が展開してくれるはずもない。
従って、マルセラも、かなりの距離を隔てた場所から辛うじて艦影を追うことしかできず、正確な戦況の報告は困難だった。
それでも、生来の野性的な視力を発揮して彼女なりに目におさめたものを、布切れの上に素早く走り書きしていく。

真剣な眼差しで書き進める彼女の口元から、思わず呟きが漏れる。
「案の定、ジョンストン提督の英国艦隊が、圧倒的に強いわね。
スペイン艦隊の艦船は、かなりの数、既にやられてる。
いきなりの接近戦、その上、乱戦になっちゃってるし、あそこまで砲撃されたらスペイン艦隊の旗艦も、きっと、もう時間の問題……。
だけど、スペイン艦隊にも粘ってる艦はいるし、まだ終わったわけじゃない」
ひとしきり書き終えると、マルセラは布切れを伝令鳥の脚に結び付け、「それじゃ、頼んだよ!」と、優しく鳥の頭を撫でた。
(此度の海戦も、本(もと)を正せば、インカ軍が勝ち残るために、トゥパク・アマル様が密かに采配されたこと。
英国艦隊も、スペイン艦隊も、本当のところは、トゥパク・アマル様の手の平の上で踊っているだけなのかもしれない。
だけど――)

これほどの距離を隔てながらも轟然たる爆音の絶え間なく響き来る方角を睨み据えながら、マルセラは、その艶やかな唇を噛み締める。
(スペイン軍の火砲にさえ苦戦を舐めてきた私たちインカ軍が、あれほどの武力を持つ者たちをわざわざ英国から呼び寄せてしまって、本当に勝機はあるのかしら…?)
それから、勢いよく頭を振って、既に上空へと舞い上がった伝令鳥を大きく振り仰いだ。
陽光を反射してキラリと煌く白い翼が、細めた目に眩しい。
(ううん、信じよう……!
トゥパク・アマル様を、そして、インカ軍を!!)

かくして、沿岸に構えられたインカ軍陣営では、水平線を遥々と見晴るかす断崖上で、洋上から吹きつける潮風に長髪を巻き上げられながら、トゥパク・アマルが鋭利な横顔を沖合いへと向けていた。
ほどなく、彼の視界の中に、マルセラの放った伝令鳥が飛び込んできた。
すっと、天に向けて差し出した彼の逞しい腕に、鴎大ほどの白色の鳥が舞い降りる。
トゥパク・アマルは素早い手つきで伝令鳥の足にくくりつけられていた布切れを解(ほど)くと、敏捷に視線を走らせる。
そして、思慮深気にその切れ長の目を細めた。
少し後方に控えていたアンドレスが、一歩、トゥパク・アマルに近づいた。
「トゥパク・アマル様、海戦の状況はどのように?」
「予想通り、英国艦隊が優勢のようだが、スペイン艦隊の一部の艦も奮戦している」

「フロレス殿の艦ですか?」
低く絞ったアンドレスの声音に、トゥパク・アマルは、そちらを僅かに振り向いた。
「この報告では、そこまでは分からぬ。
そうか――そなたは、フロレス殿と面識があるのだな」
「はい。
スペイン人にも、あのような者がいるのだと、俺の認識を大きく変えてくれた人でした」
アンドレスは、かつてラ・プラタ副王領で幾度かに渡って対決を繰り返した宿命の相手を脳裏に描きながら、ギュッと腰のサーベルを握り締めた。
あのフロレス殿なら、たとえ相手が英国艦隊と言えども、ただでは終わらぬはずです!!――と、そう喉元まで出かけた言葉を、アンドレスは黙って呑み込んだ。
(いや…英国艦隊を相手に、いくらあの者でも、経験の乏しい海戦でできることには限りがあるだろう……)
そう思った途端、不意に、背筋を言いようの無い寒気が走り、続いて強い寂寥感に襲われた。
彼の視線は、いつしか足元の断崖絶壁で砕け散る波飛沫へと落ちていた。

そのようなアンドレスの心を見透かすように、トゥパク・アマルの低く響く声が聴こえてくる。
「誰の命運も、まだ、分からぬ。
だが、アンドレス、そなたが、それほどまでに見込んだ人物なら、わたしも見(まみ)えてみたかった」
「トゥパク・アマル様……!」
かつてフロレス殿も同じことを――そう言いかけて、アンドレスは胸に押し寄せる波のような思いに、再び言葉を呑み下した。
(そう…フロレス殿も、以前、同じようなことを言っていたっけ。
あれは、ティティカカ湖畔の戦場で、初めて、あの者と戦った時だった。
トゥパク・アマル様に会いたかったと、確かに、彼も言っていた。
俺は、あの時は完全に頭に血が上っていて、まともに彼の話を聴く耳を持っていなかったが…。
もし――…もし、この反乱がはじまる前に、トゥパク・アマル様が会われていたのが、あのアレッチェやモスコーソ司祭ではなく、フロレス殿だったら?
もしそうだったら、事態はもっと違ったものになっていただろうか?
このような多大な犠牲を払うことなく、もっと平和裏(へいわり)に、多くのことが進んでいただろうか?
それとも、あのアレッチェたちがこの国の権力を牛耳っている以上、たとえフロレス殿とて、やはり、なす術は無かっただろうか……)

そのような思念に頭を占められていたアンドレスが、ハッと我に返って見上げた時には、既にトゥパク・アマルは厳然たる総指揮官の顔に戻っていた。
そのトゥパク・アマルの傍に、此度の作戦では、副指揮官であるアンドレスと同様に重要な任にあるロレンソが、敏速な足取りで近づいてきた。
トゥパク・アマルも洋上へ馳せていた視線をそちらへと向ける。
ロレンソは、トゥパク・アマルの足元に素早く跪いて礼を払うと、若者らしい鋭気に満ちた面差しを上げた。
「トゥパク・アマル様、敵方に放っていた斥候が戻って参りました。
斥候たちの報告によれば、敵将アレッチェ殿は、やはりあの陣営に!」
そう言って、彼らが陣を張る断崖上と対峙する高台に敷かれたスペイン軍陣営へと、毅然たる視線を投げた。
トゥパク・アマルも、切れ長の目で敵陣の方角を見つめ、ゆっくり頷く。

無意識に拳を握り締めながら、アンドレスが、さらに一歩を踏み出した。
「恐らく、敵方も斥候を放って、トゥパク・アマル様の所在をつきとめようと躍起になっていることかと。
いえ、恐らく、もう、ここにトゥパク・アマル様がいらっしゃることを早々に突き止めていることでしょう!」
「さもあろう。
だが、この期に及んでまで、わざわざ手間をかけてわたしの所在を探し回らずとも、わたしの方から挨拶のひとつぐらい出向いて行こうものを」
敵陣の連なる対岸に刃物のような一閃を放ち、誰にとも無く嘯(うそぶ)いたトゥパク・アマルの方へと、アンドレスもロレンソも「え?!」と瞳を瞬かせた。
「トゥパク・アマル様、今、何と?」
「そなたたちが案ずるには及ばぬ。
それより、そなたたちは、作戦通り、ぬかりなく事を進めることに全力を注いでくれたまえ」
「はっ!!」
そう恭順の礼を払いながらも、アンドレスは相変わらず険しい眼光で敵陣を睨み据えている。
「クスコ戦の時も、トゥンガスカの本陣戦の時も、あのアレッチェは、トゥパク・アマル様を捕らえるために、どれほど卑劣な手を使ってきたか。
そして、やっと捕らえたトゥパク・アマル様に牢から脱出され、どれほど地団駄踏んだことか。
あの執念深い男が、これほど近くにトゥパク・アマル様がいることを知って、どれほど喉から手の出る思いでいることか…!
あの者が、今度は如何なる鎌首をもたげてくるのか、それを思うと、俺はおぞましくてなりません……!!」
込み上げる嗚咽を抑えるかのように胸元を押さえているアンドレスの傍で、ロレンソもまた、常の鋭利な面差しをいっそう研ぎ澄ませて、案ずるようにトゥパク・アマルを見上げている。
そしてまた、彼らの後方でやり取りを見守っていた腹心ビルカパサや他の兵たちも、同様に、険しくも非常に案ずる面持ちで、トゥパク・アマルと敵陣とを交互に見渡していた。
そのような全員に真摯な視線を送ってから、トゥパク・アマルは厳然と応える。
「恐らく、そなたたちの思う通りであろう。
だが、それならばそれで、こちらにも出方というものがある」

褐色の精悍な横顔を再び水平線へと向けた彼のマントが、風の中で、漆黒の翼の如く大きく翻る。
そして、これから海と陸とで起こる激戦の展開をうらなうかのように、沈着さの陰に激情を潜ませた鋭い目元を吊り上げた。
「アンドレス、ロレンソ。
そろそろ時間だ。
行きなさい」
「はっ!!」
若者二人は俊敏に一礼すると、様々に去来する思いを胸に抱きつつも、決然と踵を返した。
こうして出陣の合図を待つ各自の兵たちの元へと急ぎながら、アンドレスは難しい表情のまま、独り言のように呟いた。
「トゥパク・アマル様は、あのように仰っているけど……。
だけど、此度の作戦、トゥパク・アマル様の御身にとって、あまりに危険ではないだろうか」
横を歩む己の横顔を、いつしか、じっと見入っているアンドレスの方へと、ロレンソも視線を返す。
「ああ…そうだな。
わたしも、そなたと同じ思いだ。
できることなら、このような危険な作戦の前面に出られようなどとお考えになられず、当陣営内深くにお留まり頂いて、幾重にも衛兵に守られていてほしいと――心底、そう願いたい心境だ」

「ああ、本当に!!
俺も、全く、君と同じそのままの思いだよ!」
二人は小さく息をついた。
しかし、再び前方に向き直り、歩調を速めながら、「だが、トゥパク・アマル様のお考えも理にかなっているとは思う」と、ロレンソが言葉を継ぐ。
「ロレンソ…!」
「アンドレス、もう決まったことだ。
あとは、わたしたちにできる最善のことを成し遂げるのみだ。
そのことが、そのままトゥパク・アマル様をお守りすることにもつながるのだから」
そう応えた己の方へと、まだ何か言いたげなアンドレスが身を乗り出しかけるのを脇にしたまま、ロレンソは、ちょうど通り過ぎかけた武器庫の方へと足を向けた。
武器庫の周りを堅固に護衛する衛兵たちが、若き二人の将の到来に、礼を払ってサッと入口への道を開く。
二人が武器庫の中を覗くと、アンドレス軍やロレンソ軍に配分された武器は既に搬出され、内部はガランとかなりの隙が空いていた。

その様子に、アンドレスは再び眉間に皺を寄せる。
「トゥパク・アマル様は、武器まで俺たちに均等に配分されてしまっている。
それに、クスコの叔父上たちの元にも送ったと聞く。
ご自分の御身の護身をもっと考えられても良いのに……」
「トゥパク・アマル様は、それだけ我らの援護に期待をかけてくださっているということだろう」
そう言って、ロレンソはアンドレスの懸念を払拭するかのように、決然と力強く続けていく。
「それに、この倉庫に保管されている火器の殆どは、そもそも英国艦隊がトゥパク・アマル様にもたらしたものだ。
英国側の腹の内は見え透いているが、それでも、それなりに英国艦隊のために役立てねばならぬと、仁義に篤いトゥパク・アマル様なら、そのようにお考えになるのは当然だ。
それを思えば、此度の作戦決行において、我らがそれらの武器を供与されたのは、陛下の御心にかなっていよう」

他方、アンドレスは、キッと、鋭く友の顔を振り向いた。
「だけど、結局は、英国は俺たちの真の味方なんかじゃない!
あの者たちも、所詮は、この国をスペインから奪い取って、己の植民地にしようと狙っているだけじゃないか!!」
「そう。
だから、此度の作戦には、その先がある。
ともかく、アンドレス、そのような案じ顔は、もうやめにしよう。
そなたがそのようでは、そなたの兵たちにまで、いらぬ不安をかき立ててしまうぞ!」
アンドレスの背を軽く押しながら武器庫から離れかけて、ロレンソは、ふと相手の横顔に目を留めた。
先刻までの険しく難しい表情は陰を潜め、その面差しには、今は深い悲しみを湛え、じっと倉庫の奥の一点を見つめている。
ロレンソは、黙って、その視線の先を追った。
そこには、ただ火薬の詰まった多くの硝子壜が整然と並べられているのみである。
「アンドレス…?」
ロレンソの声に我に返ったアンドレスが、咄嗟に大きな瞳を瞬かせた。
「あ…いや、すまない。
ちょっと気をとられて…」

それから、サッと目を伏せて苦悶の面持ちで口ごもる彼の方に、ロレンソは再び静かに問いかける。
「アンドレス、何を考えていた?」
「いや…」
「アンドレス?」
「あの硝子壜を見て、ちょっとフランシスコ殿のことを思い出したのだ。
フランシスコ殿の天幕にあった山のような酒壜のことを……」
そう語るアンドレスの脳裏に、かつてクスコの陣営にいた頃の己とフランシスコのことが、激しく交錯しながら甦っていた。
トゥパク・アマルに対する激しい思慕と疑心暗鬼との葛藤の中、酒に溺れ、苦悶の中で己を見失っていったフランシスコの姿、そして、為す術も無く戸惑うばかりであった自分自身の姿――。
アンドレスは胸苦しくなって、思わずギュッと瞼を伏せる。

(しかも、フランシスコ殿を追い込んだ最たる張本人は、俺自身であったかもしれないのだ…!
あの時、俺さえもっとしっかりしていれば、フランシスコ殿がアレッチェに拐(かどわ)かされてトゥパク・アマル様を裏切ることも、彼が命を落とすこともなかったかもしれない……!!)
アンドレスの伏せた瞼が震えている。
「アンドレス……」
悲痛な面持ちで俯(うつむ)く朋友の姿を居た堪れぬ思いで見つめながら、しかし、ロレンソもすぐには返す言葉が見つからず、苦渋の滲む唇を噛み締めた。
暫し継ぐ言葉を探しあぐねているロレンソの傍で、アンドレスは、まるで懺悔の言葉を吐き出すように続けていく。
「トゥンガスカの本陣戦で、トゥパク・アマル様がアレッチェの陰謀にはめられ、そして、無事にご帰還されるまで、あまりに怒涛のように日々が過ぎて、俺は、まともにフランシスコ殿の死を悼むことさえしていなかった。
いや、フランシスコ殿だけじゃない。
反乱がはじまってさえいないのに暗殺されたブラス殿。
本陣戦でアレッチェの手にかかったフィゲロア殿…!
そして、ミカエラ様たちをお守りして敵弾に倒れたオルティゴーサ殿!
それに、とても数え切れないほどの無数の兵たち……!!」

「アンドレス!!」
ロレンソの手が友の肩を力強く掴み、完全に俯いてしまった相手の顔を正面に向き直らせた。
そして、鋭くゆるぎない面差しで、アンドレスの顔に真っ直ぐ目を据えた。
「アンドレス、そなたの思いは、彼の地に旅立った者たちに、必ずや、しかと伝わっていよう。
それに、そのように彼らを悼む思いがあるのなら、なおのこと、今、我々にできることは、一刻も早くこの戦(いくさ)に決着をつけ、これ以上の犠牲を増やさぬことだ。
その上、そなたは、今、トゥパク・アマル様の副官ではないか!
そなたの働きいかんで、この戦の行く末を左右するほどの影響力を持つ立場にあるのだ。
そなたの思いが、此度の決戦でインカ軍の力の源となり、守護の力となるよう祈っている!!」
ロレンソの険しいほどに厳然たる口調に、アンドレスもハッと目を見開いた。
そして、我を取り戻したように頷く。
「そうだな…今こそ、前をしっかり向いていなければ……!」

それから、己の肩を握り締めている友の逞しい褐色の腕に、彼も手を添え、力強く握り返した。
「ありがとう、ロレンソ。
インカの神々の加護が、君と君の兵たちの元に常にあらんことを!!」
ロレンソも力強く頷き返す。
「そなたとそなたの兵たちにも、そう願わん!
アンドレス!!」
こうしてアンドレスとロレンソたちが出立した頃、遥々と海岸線から水平線までを見渡せる断崖上のスペイン軍陣営では、スペイン軍総指揮官アレッチェもまた、険しい視線を洋上へと馳せていた。
海戦の戦況視察に赴かせた哨戒艇の報告では、己のスペイン艦隊は甚大なる打撃を受け、麾下(きか)のスペイン艦隊中では最も高性能で強靭なはずの旗艦さえも、早々に戦闘不能の破船と化しつつあるという。
フロレス艦が辛うじて反撃を試みたとの報告もあったが、それも、さしたる戦果には結び付いていない。
現在も海戦は続いているとはいえ、断片的な報告を紡ぎ合わせても、スペイン艦隊の劣勢は明らかだった。

アレッチェは、苛立たしげに、チッと舌を鳴らす。
(ベルナルド旗艦艦長は、案の定、全く使えぬ男であった。
苦肉の策で、急遽、副指揮官に抜擢したフロレスも、所詮は俄(にわか)仕込みの小手先の力量。
あの英国艦隊の敵とは成り得なかったということか)
しかしながら、自軍の艦隊の非常な危機的状況にも関わらず、アレッチェの思考は不気味に冷静であった。
早朝は曇天のために灰色がかっていた空も、今は地上の戦のことなど他人事のように爽快に晴れ渡り、生ぬるく湿った潮風をしきりに全身に吹きつけてくる。
(もともとスペイン艦隊の勝機など、あのジョンストン艦隊を相手に、どう楽観的に見積っても、ありようの無いものだった。
邪魔者のスペイン艦隊を始末した暁には、ジョンストンどもは、いっそうの士気を高め、いよいよこの陸岸に押し寄せてくるであろう。
つまるところ、本当の勝負は、英国艦隊が陸岸に迫り来てからの、この砦で陣を構える我が軍との戦闘によって決することになる。
従って、フロレス、もし、おまえがまだ生き延びているならば、おまえの役割は明白だ。
一艦でも多くの英国艦に損害を与え、陸岸に攻め上る敵艦の勢力を最大限に殺(そ)ぐこと――たとえその身に代えようがな)

心の内で冷淡にそう呟くと、アレッチェは、その冷徹な眼光を己の立つ断崖上に広々と展開する砦の城壁へと向けた。
それら長大な砦の砲門に延々と据えられた多数の黒光りする大砲たちは、いつ敵艦隊が現れようとも、すぐさま砲撃の雨霰を見舞えるよう、沖合に向けて完璧に照準済みである。
しかも、それら無数の各砲には、強烈なぶどう弾が装填され、閉じた砲門の陰でじっと俯角をつけている。
それらの砲列を隙無く眺め渡した後、アレッチェは、再び上げたその彫りの深い横顔を、今度はインカ軍陣営の方角へと向けた。
不意に、冷酷なほどに冷静だったその目元が、険しく吊り上がる。
(トゥパク・アマル、あの男が、あそこにいる!!
あの忌々しいインディオの首領めが!!)

次の瞬間、アレッチェは、己の指が無意識に腰の銃を引き抜きかけていることに気付いて、ハッと口の端を歪めた。
抑えようにも全身の血液がフツフツと沸き立つような感覚に突き上げられながら、そのような己に内心で激しく毒づかずにはいられない。
(落ち着け!
あのトゥパク・アマルのこと、今更、逃げ隠れなどすまい。
ここは頭を冷やしておかねば、周到に事を運べぬぞ。
今度こそ、取り逃がすわけにはいかぬのだから)
アレッチェは、その黒々とした前髪からのぞく険しい黒眼を炯々と光らせ、インカ軍陣営を切り裂くように睨(ね)めつけた。
そして、がっしりとした肩と分厚い胸板を包む上質な軍服の襟元をグッと正し、腰の銃を据え直す。
(いずれにしろ、インカ側は、ここで英国艦隊と我らが戦闘状態に入れば、ここぞとばかり、必ずや邪魔立てを仕掛けてくるに相違あるまい。
英国艦隊を迎え撃つと同時に、インカ軍への警戒と対抗策も万全を期さねばならぬ)

かくして、再びインカ軍陣営――。
その頃、己の天幕に戻ったトゥパク・アマルもまた、素早い動作で出陣の身支度を整えていた。
幾多の戦火を馳せて鍛え抜かれた肉体に、重厚な革と綿でできた分厚い胸甲を纏(まと)っていく。
今では彼の身の回りの世話をしているリノが、それを助けていた。
そうしながら、その天幕内に参集した腹心ビルカパサをはじめとした数名の臣下たちの方へと、その端正な輪郭を向ける。
相変わらず湖面のようにゆるぎない静かな面差し――だが、その深い漆黒の瞳の中に燃え上がる蒼い炎を認めて、ビルカパサたちは、ハッと、いっそう襟を正す。
そのような家臣たちの前で、トゥパク・アマルが低く沈着な声で語り出した。
「今、この瞬間も海上で行われていよう海戦で英国艦隊がスペイン艦隊を破れば、いよいよ英国艦隊はこの陸岸に向けて押し寄せてくる。
そうなれば、今度は、陸で待ち構えるスペイン軍陸軍本隊と英国艦隊との決戦となる。
我々としては両者が相討ちになってくれることを望むところだが、いかにジョンストン提督指揮下の精鋭の英国艦隊とて、陸岸に据えられた砦からの多数の砲撃と互角に戦うのは容易ではなかろう。
しかも、当地のスペイン軍本隊を統率するのは、あのスペイン軍総指揮官アレッチェ殿だ。
英国艦隊にとって、ますます分(ぶ)のいい相手とは言いがたい」
そう言って、トゥパク・アマルは、一旦、息を継ぎ、思慮深げに鋭利な目元を細めると、さらに深遠な声音で続けていく。

「それ故、我々としては、スペイン軍陸上部隊を撹乱するのが此度の作戦の最初の目的であり、そのために既にアンドレスたちが出陣したのは周知の通りだ。
我らの本格的な軍事行動は、実際に英国艦隊が姿を現し、スペイン軍陸上部隊との戦闘が開始され、その戦況の流れを見てからだ。
だが、あのアレッチェ殿のこと故、当然ながら、そうした我らの動きをも予測しておろう。
ならば、敵を撹乱しはじめるのは、少しでも早い方が良い」
「はっ!
トゥパク・アマル様!!」
周囲の者たちが恭順の礼を払う姿を変わらぬ沈着な眼差しで見届けながら、トゥパク・アマルは、リノが急いで掲げ持ってきた重厚な愛剣と銃を受取った。
そして、それらを敏捷な手つきで腰に装着する。
そうしながら、精悍な横顔で光る切れ長の目を、いっそう研ぎ澄ませた。

「先刻、アンドレスも申していたように、わたしを再び捕らえんとするあのアレッチェ殿の執念はひとかたならぬものがある。
本来は冷徹なほどに冷静、且つ、有能な人物だが、わたしの身のこととなると、いかにも執拗で、あの者らしからぬほどバランスを欠く。
言わば、それが、あの男の弱点だ。
ならば、我らとしては、それを利用せぬ手はない」
「はっ!!」
臣下の兵たちが力強く礼を払う。
やがて、それらの兵たちの間から重臣ビルカパサが、常の感情統制のいきとどいた豪胆な面差しを上げ、トゥパク・アマルを真っ直ぐ見つめた。
「それで、あのアレッチェ殿を少しばかり挑発に出向こうと?」
「さよう」と、トゥパク・アマルは、その輪郭にかかった長髪を鋭い手つきで掻き上げる。
「多少なりとも顔を見せてやるだけでも、あの者を浮き足立たせるには十分であろう。
欲している餌(えさ)をちらつかせ、引っ込める。
使い古された心理戦の常套手段だが、今のあの者の頭に血を上らせるには少なからず効き目があろう」
「えっ、餌――でございますか……!」
トゥパク・アマルが己自身のことを平然と「餌」呼ばわりしたさまに、ビルカパサも他の廷臣たちも返す反応に困惑し、一瞬、目を白黒させながらサッと視線をそらした。
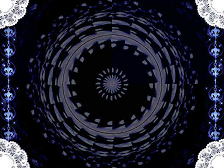
そのような彼らの様子には頓着せずに、トゥパク・アマルは、変わらぬ淡々たる調子で続けていく。
「アレッチェ殿の本来の冷厳さと隙の無さで、虎視眈々と万全なる態勢のままに英国艦隊を迎え撃たれては、こちらとしては願わしくない。
それに、後の我らとの決戦本番の際に、あの者が踏み外しやすくなるよう、呼び水を撒(ま)いておくことも必要だ」
「はっ!!」
ビルカパサたち家臣一同が、再び我を取り戻し、決然と恭順を示した。
そして、深く礼を払いながら、それら臣下の者たちがトゥパク・アマルに問う。
「して、トゥパク・アマル様、陛下のお供を仕(つかまつ)ります兵力は如何ほどにいたしましょう?」
「此度は戦闘が目的ではなく、あくまで敵を心理的に撹乱するのが目的だ。
我らとて、むやみに尊い兵力を失うわけにはいかぬ。
増してや、今は、本番戦を後に控えている大事な時。
よって、此度に関しては機動性を重視し、少数の騎兵でよかろう」
そう応えながら、トゥパク・アマルは、ビルカパサの方へと素早く視線を走らせる。
「それから、此度は、あれを持参せよ」
「はっ。
万事、心得てございます!!」
トゥパク・アマルは頷くと、既に敏速な足取りで天幕出口へと向かいながら、金糸の織り込まれた戦闘用の黒マントをその長身にバサリと羽織った。
「今、この瞬間にも、海上では海戦が着実に進んでいるはずだ。
我らにも、残された時は少ない。
即刻、出立する」
「御意!!」
 それから間もなく、逞しい白い愛馬に跨ったトゥパク・アマルが、インカ軍の堅固な陣門から猛々しい勢いで翔け出して来た。
それから間もなく、逞しい白い愛馬に跨ったトゥパク・アマルが、インカ軍の堅固な陣門から猛々しい勢いで翔け出して来た。
彼は、直下の重臣たちらしく華々しく武装した騎馬のビルカパサ及び十数名の家臣たちを伴って、黄金色の砂塵を蹴散らしながら陣営から駆り出して行く。
そして、その後を、数十名の騎兵たち――厚い革の胸甲に身を包み、銃とインカの投石器オンダ(註参照)とで武装している――が、軽やかな身のこなしで、駿馬を駆り立て付き従っていく。
(【註】オンダ:インカ時代の投石器。縄の両端を手に持ち、腕の回転力を利用して石を遠くに飛ばす仕組みになっている。硬い鉄の兜さえ穴が開くほどの威力を持ったと言われる。)
いかにも己らの存在を顕示するかの如くに、隊列の先頭を疾走するトゥパク・アマルを中心に、勇猛な雄叫びを上げながら愛馬を蹴立ててゆく彼らの厳めしい輪郭を、風にたなびく長髪がいっそう凛々しく引き立てている。
そのままトゥパク・アマルたちは怒涛の勢いで彼らの陣の敷かれた岸壁をくだり、疾風さながらに、敵陣の据えられた数キロ先の断崖を駆け上りはじめた。

ほどなく彼らの姿をとらえたスペイン軍陣営の衛兵が、転がるようにして彼らの総大将アレッチェの元へと素っ飛んでいく。
「ト…ト…トゥパク・アマルが、こっちに向かっています!!」
「なに?!」
厳然たる隙の無い面持ちで、黒々と磨き抜かれた砦の砲台群を見回っていたアレッチェが、ギッと、鋭い眼光で振り向いた。
「トゥパク・アマルだと?!」
「は…はい…!!
アレッチェ様…!
インカ兵たちを引き連れて、こ、こちらに……!」
アレッチェは、すっかり慌てふためいて素っ頓狂な声を上げている衛兵の胸倉を、拳で乱暴に掴み上げた。
人を人とも思わぬような数々の冷酷な彼の所業を見知っているだけに、衛兵は己の身の危険を感じて、ヒッと、全身を強張らせた。
他方、当のアレッチェは、その冷徹な風貌に、しかしながら、今は、さすがに驚きと不審の形相を隠せぬまま、相手の顔面を穴の空くほど見据えている。
「大軍か?!」
「いえ…せいぜい4、50人の手勢かと……!」
「たった4、50だと?!」
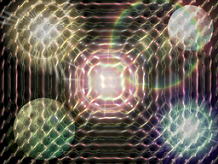
(トゥパク・アマル、何を考えている?!)
己に押さえ込まれた胸元を苦しそうに押さえながら息も絶え絶えになっている衛兵を、アレッチェは、バッと地に投げ捨てた。
それから、その強靭な長い足で、大股に見張り台へと駆け上る。
険しく目元を聳(そび)やかせて見下ろす視界の中に、まさに衛兵の報告通り、あのトゥパク・アマルが、僅かな兵たちと共に、こちらに白馬を馳せてくる姿が映る。
(トゥパク・アマル――!!)
アレッチェは、ギリリと奥歯をきしらせた。
そして、無意識のままに、苛つく指先を腰の銃に走らせ、それを荒々しく握り締める。
不意に、アレッチェの脳裏に、これまでトゥパク・アマルと直に見(まみ)えた様々な因縁の場面が、雷光の如く迸(ほとばし)った。
最後にトゥパク・アマルと言葉を交わしたのは、いつだったか?――クスコの地下牢での、あの拷問の時が最後であったろうか。
(処刑まで待とうなどと手ぬるいことを考えずに、いっそあの時、あそこで息の根を止めておけば良かったのだ。
いや、そもそも、あのリマでの最後の接見の時、己の直観に従って、あの場でトゥパク・アマルを始末さえしていれば……!!)
実際、あの忌々しい場面は、今もアレッチェの脳裏に澱(おり)のようにこびりついて離れなかった。
『マキャベリズムの創始者の言葉を知っているか?』
あの時、氷のように響く己の言葉に、トゥパク・アマルは一切の感情を殺したように、重い沈黙を守っていた。
『彼は、被征服地の支配を安全にするためには、その国を支配していた王族の血統を抹殺することが必要だと述べている。
四等身に至るまで絶滅すべき、とね。
もし、何か事を起こせば、それは、逆賊として、インカ一族の合法的殺戮の理由を、我々スペイン側に与えることに他ならない。
それをよく覚えておくことだ』
やがて、沈黙を守っていたトゥパク・アマルが、ゆっくりと振り向いた。
それは、もはや感情の無い、能面のような表情だった。
『我々一族は、この地の民を守るためにある。
結果、どのようなことになろうとも、それは自ずと覚悟の上』

一方、アレッチェがそのような想念に憑かれている間にも、今、この現実の中では、トゥパク・アマルたち一団が、たちまち距離を詰めてくる。
まだ幾ばくかの距離を隔ててはいたが、スペイン軍陣営の高所から、憎悪と執念に燃える鬼のような凄まじき形相で己を見下ろす敵将の姿を見つけると、トゥパク・アマルもまた、愛馬の手綱を引いた。
そして、サッと、その腕を鋭く払って周囲に合図を送ると、ゆっくりと馬の足を止めていく。
一見、感情の揺らぎの無い、変わらず沈着な彼の面差し――だが、その瞳の奥にも、蒼い炎がメラリと燃え上がる。
トゥパク・アマルとアレッチェ――はからずも運命の宿敵となった二人の焼け付くような視線がぶつかり合い、見えざる火花が激しく宙に飛び散った。
その頃、インカ軍陣営に設けられた広大な治療場の片隅に、干しかけの薬草を手にしたまま、空を見上げるコイユールの姿があった。
吸い込まれるように一心に上空に見入っている彼女の傍に、同僚のインカ族の少女が近づいた。
少女は持参してきた洗い立ての薬草を抱えたまま、不思議そうに小首をかしげる。
「空がどうかしたの?
コイユール?」
問いかけられたコイユールは、くっきりとした目元を研ぎ澄ませ、唇を引き結んだ真剣な横顔で、きっぱりと頷いた。
その瞳は、まだ蒼穹を真っ直ぐにとらえたままである。
「空の気配が、何か違ってきているような気がするの」
「へ?
空の気配が違ってきてるって、それ、どういう意味?」
相手の少女が、ますます首を大きくかしげながら、つぶらな黒い瞳を瞬かせた。
それから、彼女も大きく天空を振り仰ぐ。
見上げる空は爽やかな初夏の晴天に彩られ、ゆったりと流れる柔らかそうな純白の雲間からは、煌く陽光が差し込んでいる。

少女は褐色の腕を上げて手びさしをしながら、眩しそうに目を細めた。
「特に変わったこともないと思うけどなあ。
でも、まあ、コイユールがそう言うんなら、きっと、そうなんだろうねえ」
そう言って振り向くと、相変わらずコイユールは微動だにせず、熱心に上空に見入っている。
その細い肩にかかった長い黒髪のおさげだけが、ただ静かに風に揺れていた。
やがて、そんなコイユールの傍をゆっくりと離れ、持参した洗い上がりの薬草を作業台に乗せながら、少女がポツリと言う。
「嘘みたいに静かよねえ。
まだ、ここは……」
コイユールも、ハッと振り返り、手にしたままだった干しかけの薬草を作業台の上に広げはじめた。
そして、頷きながら、まだ殆ど負傷兵のいない閑散とした広い治療場を、遥々と見渡していく。
「本当に、そうね。
できることなら、このまま、ずっと静かだったらいいのに。
前の戦さで怪我をした負傷兵の人たちも、せっかく良くなったばかりでしょう。
また、ここが、たくさんの人たちで埋まっていくのかと思うと、やっぱりとても気が重いわ」
そう呟くコイユールの口元から、小さく溜息が漏れた。

「そうだね」と、隣の少女も深く頷く。
「でもさ、コイユールもあの時いたけど、トゥパク・アマル様がわざわざここに来て、この治療場を拡張していったくらいだもん。
今回は、これまで以上の激戦になるってことでしょう?」
コイユールが苦渋の横顔を俯(うつむ)かせる先から、少女も吐息交じりに、さらに続けていく。
「確かに、私だって、早くこの戦さが終わって、あのひどい奴らがいなくなってほしいって、心底、願ってる!
だけど、この戦さのせいで、トゥパク・アマル様に何かあったらって思ったら、私、とっても憂鬱よ!!」
少女は、いっそう深く息をついて、今度は神妙な案じ顔でポツリと呟いた。
「でも、もう、さっきトゥパク・アマル様は、陣営をご出立されたって聞いたわ……。
それに、その前には、アンドレス様やロレンソ様もご出陣されたって」
「――!」
薬草を選り分けていたコイユールの華奢な指先が、瞬間、ピクリと止まる。
相手に聴こえようはずもないのだが、にわかに高まり出した鼓動を悟られまいとするかのように、彼女はサッと作業台を離れた。
そして、「残りの薬草を洗ってくるわね」と、すかさず踵を返す。

その場を急ぎ足で立ち去りながらも、強い胸苦しさを感じて、コイユールは慌てて木陰へと駆け込んだ。
先刻まで、あれほど静かに感じられていた頭上の樹木が、今は、妙にざわついて感じられる。
彼女は胸元を強く押さえたまま、フーッと、身体の奥底から深々と息を吐き出した。
(ここは陣営なのだから、アンドレスが戦場に出かけていくのは当たり前なのに…。
だけど、いつまでたったって、こんな不安な気持ちに慣れることなんて無い!!)
そう心の中で囁きながら、暫しの間、涙の滲みかけた目を伏せていたが、やがて、不意に傍の小枝に舞い降りてきた小鳥の気配に目を上げた。
午後の陽だまりの中で、元気に囀(さえず)りながら、自分の周りで楽しそうに小枝から小枝へと飛び交う2羽の小鳥たちの姿は、とても愛らしく微笑ましい。
コイユールの横顔にも、思わず微笑みが浮かんだ。
その瞬間、彼女は、ふと思い出したように、スカートの上から己の大腿に手を触れる。
それから、素早くスカートを軽くめくって、己の足に結びつけていた短剣を取り出した。
クスコで遠征に発つ際、アンドレスから渡された王家の短剣――それは、かつて敵兵に襲われそうになった時、己の身を護ってくれたことがある。
それ以来、その短剣を彼の分身の如くに、いっそう大切に想ってきた。
精緻な彫刻の施された黄金の鞘(さや)と柄が、樹間から射しこむ木漏れ日を反射して、キラキラと眩い繊細な光を放っている。

無意識に彼女の褐色の指先が優しく剣全体をなで、それから、思い余ったように、ギュッと強くそれを抱き締めた。
今、再び凛とした光を取り戻した瞳が、真っ直ぐ蒼穹を振り仰ぐ。
見上げる天空では、数羽のコンドルが、その巨大な漆黒の翼を大きく広げ、宙を切り裂くように力強く滑空していた。
他方、同じ頃、作戦準備を進めつつ、近隣の森陰に身を潜めながら密かに進軍していたアンドレス軍とロレンソ軍の兵たちは、遥か前方の視界に突如として飛び込んできた信じがたい光景に、各自の目を疑っていた。
彼らの視線の先にあるのは――スペイン軍の砦に据えられた見張り台から、遠目からもありありと分かるほどに黒々としたオーラを漲らせて眼下を睨(ね)めつけているアレッチェの姿と、そして、幾ばくかの距離を隔てた場所で、見慣れた白馬に跨ったまま、その敵将の方角へと鋭い輪郭を向けている人物の姿――!!
「――!
あれは…まさか!!
トゥパク・アマル様……?!」
愕然と震える声を漏らすアンドレスの脇で、ロレンソも瞳を見開いたまま完全に声を失っている。
「おい!!
ロレンソ、あれは、どういうことだ?!
まだ作戦決行前なのに、どうしてトゥパク・アマル様が直々に敵軍の前に?!
しかも、あのように少数の兵だけを連れて…!!」
反射的に友の肩を掴んで半狂乱の声を上げ出したアンドレスと呼応するかのように、彼らの元にいるインカ兵たちの間にも、波紋のように驚嘆のざわめきが広がっていく。
ロレンソは素早く兵たちを振り仰ぎ、鋭く叱咤した。
「シッ!
静粛に!!」
それから、アンドレスにも険しい顔で向き直り、声を潜めながらも決然と言う。
「アンドレス、落ち着け!
トゥパク・アマル様のお考えあってのことだ。
それに、ビルカパサ様たちもお傍についておられる。
我らが案ずることではない」
そうは言いつつも、やはり固唾を呑んでいるロレンソの傍で、アンドレスや他の兵たちは相変わらず愕然と呆然の面差しで目を見張ったまま凝固している。
その時、アンドレスたちの視界の遥か先で、トゥパク・アマルの胸元に陽光が射し込み、その光を反射して、何かがキラリと鋭い閃光を放った。
ハッと、彼らがその光源へと目を凝らすと、トゥパク・アマルの胸には、かつてのインカ皇帝が戦時に愛用したのと同じ、太陽の紋章を象(かたど)った巨大な黄金製の首飾りが煌いていた。
さらに、トゥパク・アマルの背後に控えていたビルカパサが、その逞しい腕にガッチリと携えていた太く丈のある棒のようなものを天高く振り上げ、それを大きく一振りした。
その瞬間、パァッと、鮮やかな虹色の旗が蒼天に悠然と翻る。

「虹色の御旗(みはた)だ――!!」
アンドレスが頬を紅潮させながら、思わず小さく叫びを上げた。
虹色の御旗――インカ帝国時代、数多(あまた)の勝利を飾ったインカ軍が携えていた七色旗。
太陽の光を象徴する七色に染め上げられたその旗は、インカの末裔たる彼らにとって、今も非常に特別なものであった。
「インカ皇帝を象徴する黄金の太陽の紋章…そして、インカ帝国の栄光を表わす虹色の御旗……。
トゥパク・アマル様は、挑発しておられるのだ…!」
さすがに瞳を揺らしながら上擦った声を漏らすロレンソの脇で、アンドレスも生唾を呑み込んだ。
「挑発…!
あのアレッチェを……!!」
その時、何の前触れも無く、不意にスペイン軍陣営の砲門が一斉に開き、間髪入れずに無数の砲台が轟然と火を噴いた。
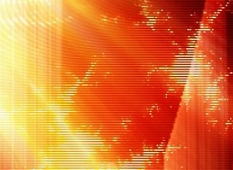
「――!!」
アンドレスが反射的に飛び出しかけた腕を、すかさずロレンソの強靭な手が押さえ込む。
「落ち着け、アンドレス!!」
そして、「見ろ!」と、相手に向かって敏捷に視線で合図する。
アンドレスは涙さえ滲みはじめた大きな瞳を激しく揺らめかしながら、ロレンソに促されるままにそちらを振り仰いだ。
その視線の先では、再び轟々と放たれる砲弾群と、それに続く銃弾の雨あられの凄まじさにもかかわらず、トゥパク・アマルたちは先刻の位置から微動だにせず、変わらぬ沈着な面差しに、いっそう挑戦的で不敵な笑みさえ浮かべながら、スペイン軍陣営を見据えている。
流れ来る爆風でトゥパク・アマルの纏う黒マントと漆黒の長髪が幾度も大きく宙に舞い上がり、はだけた胸甲の胸元では、黄金の太陽像がますます眩く光り輝いている。

さらに、その彼の背後では、大きな虹色の御旗が、黒い疾風の中で、さらなる鮮烈な威光を放ちながら力強く翻っている。
アンドレスもロレンソも、そして、彼らと共にいる兵たちも、昂ぶる興奮にいよいよ顔を上気させながら、恍惚と息を詰めた。
「トゥパク・アマル様は、完璧に敵方の射程を読んでおられる…!」
昂然と呟くロレンソの声音に、アンドレスたちも、ただただ吐息と共に幾度も頷き返すばかりである。
その時、突如、砲撃と銃撃の嵐がピタリとやみ、と同時に、スペイン軍陣営の軍門が重々しい軋み音と共に開け放たれた。
そして、背後に無数のスペイン兵たちを従えたアレッチェが、艶光りする黒馬に跨って姿を現した。
鋼鉄の甲冑に包まれたガッチリと強靭な両肩が陽光を反射し、彫りの深い輪郭の造形では、他者を射竦めずにはおかないあの冷徹な目がギラついた光を放っている。
その黒々とした瞳が、ついに眼前に姿を現した宿敵を焼き殺さぬばかりの激しさで睨(ね)めつけ、皮相に歪んだ口元からは憎悪に濡れた声が放たれる。
「トゥパク・アマル――反乱の大罪にあきたらず、脱獄囚に成り下がった挙句、今度は国まで英国に売り払った売国奴め。
その上、この期に及んで、まだ悪あがきを続けるつもりか」

他方、胸元の黄金像が四方に放つ煌く閃光のためなのか、その全身に黄金色の覇光を纏ったかに見えるトゥパク・アマルが、愛馬の手綱を繰りながら、アレッチェの方へと真っ直ぐ向き直る。
彼は、ゆるぎない断固たる口調で言い放った。
「何とでも言うが良い。
このインカの地の民を護るためならば、わたしは、どのような罪でも重ねよう」
しかし、アレッチェは、いつにも増して険しく眉を吊り上げ、忌々(いまいま)しげに大地に唾を吐き捨てた。
「トゥパク・アマル。
おまえは、この期に及んで、まだそのような綺麗ごとを。
もはや実体無き亡国の皇帝をいつまで気取っているつもりだ。
今や、この国の土地という土地、人という人、家畜という家畜、いや、この足元の草のひとふさまで、ありとあらゆるものは、我がスペイン国王が所有するものなのだ。
愚かにも、おまえの祖先も、おまえ自身も、いつまでもその現実を認めようとせず、そのために、どれほど無駄な血が流されてきたことか」
そう言って彼はトゥパク・アマルの言葉を冷酷に一掃すると、妖魔の如く蔑みと憎悪に満ち満ちた形相で相手を睥睨した。
そのようなアレッチェの言葉を、能面のような顔色の見えぬ表情で聞いていたトゥパク・アマルだったが、ふと、その横顔に視線を向けたビルカパサは、思わずハッと息を詰める。
いつにも増して鋭利に研ぎ澄まされた主(あるじ)の切れ長の目元が、錯覚とは思えぬほどハッキリと、強烈な白光を帯びてくるのを見てとったからだった。
「アレッチェ殿。
口を慎まれよ。
それ以上、そなたの汚れた口や手で、我らの神々の地を穢(けが)すことは許さぬ」
ビルカパサの目の中で、そう語るトゥパク・アマルの長髪がメラリと宙に浮いたかと見えた途端、突如、ゴウッ――と、地を震わす唸り音と共に辺りの風が強まった。

そして、それは、みるみる勢いをはらんだ強風となって、その界隈一帯を巨大な鎌で刈り取ろうとするかの如くに、激しく凶暴に吹き荒れはじめた。
「な、なんだ……?!
なんだ、この風は?!!」
スペイン兵たちが、驚愕と混乱の喚(わめ)き声を上げながら、にわかに浮き足立つ。
トゥパク・アマルを執拗に睨み据えていたアレッチェもまた、その射るような視線をはずして、素早く周囲を振り仰いだ。
そうしている間にも、スペイン軍の砦まで巻き込みはじめた暴風は、高みの砲門に据え付けられた頑強な大砲さえも容赦無くガタガタと激震させはじめた。
他方、地上では、渦巻きながら吹き上がる砂塵に視界を奪われたスペイン兵たちが、微細な弾丸の如く叩き付けてくる小石たちから身を守ろうと慌てふためき、落馬して足を滑らせたり、矢のような突風に武器を吹き飛ばされたりしている。
さらに、頭上では、雷光の閃(ひらめ)く暗雲が津波さながらに押し寄せ、先ほどまでの蒼空をたちまち押し隠しながら、天も地も灰黒色の世界へと塗り替えていく。

光が遮られた暗澹(あんたん)たる大地の上では、勢いのやまぬ轟々たる爆風になぶられるスペイン兵たちが、その凶暴な風から僅かでも逃がれようと、身をかがめて必死に地を這い回っていた。
そんな彼らの中から、恐れ慄きとも罵声ともつかぬ叫び声が上がり出す。
「化け物だ……!
あのインディオ、化け物だ――!!」
そのような敵兵たちの様子を、強風に翻る七色旗の下で、今も一糸乱れぬ隊列を保つインカ兵たちを従えた騎乗のトゥパク・アマルが、黒マントを翼のように大きくなびかせながら超然と見下ろしていた。
かくして、その頃、敵の砦への進軍途上、その砦の正面でめまぐるしく展開しはじめた一連の攻防を目(ま)の当たりにしてしまったアンドレスやロレンソたち一行は、誰もがその光景に釘付けられたまま、完全に足が止まっていた。
「なあ、アンドレス、トゥパク・アマル様は、その…何か、こう、嵐を呼ぶお力とか、そういった特殊な能力をお持ちなのか?」
固唾を呑みながら恍惚と擦れ声を漏らすロレンソを、暴風に吹き飛ばされぬよう地に突き立てたサーベルを懸命に握り締めたまま、アンドレスが振り向いた。
「え …?!」

二人は興奮に膨らんだ鼻孔を互いに突き合わせながら、瞬きすら忘れた瞳を暫し見交わし合う。
それから、やがて戸惑いがちな表情で、アンドレスがゆっくりと首を振った。
「さ…さあ…?
俺にも分からない」
ロレンソは吹き付ける砂塵を避けようと瞼(まぶた)の上に手びさしすると、蒼光りする稲妻に照らし出されるトゥパク・アマルの遠いシルエットへ視線を返した。
そして、眩しそうに目を細める。
「そういえば、こんなことが、以前にもあった。
あれは、そう、確かトゥンガスカの本陣戦の時だった。
トゥパク・アマル様がアレッチェの謀略にはめられて囚われた日、一寸先も見えぬほどの激しい豪雨となり、その最中、天地も裂けんばかりの凄まじい落雷が敵陣を襲ったのだ」

「そ…そんなことが――…!」
「ああ。
そなたは、ソラータに遠征に発った後のことだから、知る由(よし)もなかろうが」
「そんなことが……」
昂然と呟きながらアンドレスが再び前方に向き直ったその時、不意に、遥か彼方のトゥパク・アマルが、サッと、鋭い視線をこちらに投げた――ように二人には見えた。
「え?!
ロレンソ、今、トゥパク・アマル様が、こっちを見なかったか?!」
「あ…ああ!
確かに、こちらをご覧になられたような…!」
二人は顔を熱く火照らせ、ますます食い入らんばかりに身を乗り出した。
そんな彼らに、トゥパク・アマルの遠いシルエットは、今度は、その腕を素早く左右に振って宙を切った。
それは、完全に瞬間的な動きであった。
が、その動きを見た途端、石つぶてか何かを強烈に頭に投げつけられたかのような激しい衝撃を覚えて、「アッ――!」と、アンドレスは咄嗟に額を押さえ込む。
「アンドレス?!」
「つぅ……――」
暫しの間、本当に何か固いものを叩きつけられたかのように、きつく目を閉じて身を屈(かが)め、額を押さえていたアンドレスだったが、やがて、パッと大きな瞳を見開いた。
そして、ロレンソと彼の一行に敏捷に視線を馳せる。
「ロレンソ、君たちの軍は、計画通り、このまま進軍を続けてくれ。
俺たちの軍は、この混乱に乗じて、トゥパク・アマル様のご一行の背後を速攻で迂回し、敵陣の反対側に回る!」
「何を突然…!
二手に分かれると言うのか?」
「ああ、そうだ。
君の軍と俺の軍と、あの砦の両翼に二手に分かれる」
そう言って、アンドレスは、彼方のトゥパク・アマルの方へと顔を振り向けた。
「今、俺はそのように――」
「トゥパク・アマル様のご意志を受け取ったと?」
問いながら、ロレンソは思慮深い指揮官の目に戻って、頤(おとがい)に褐色の指先を添える。
アンドレスは、力強く頷き返した。
「ああ!
確かに、俺は、そう受け取った!」

さらに、アンドレスは口早に続けていく。
「それに、可能であるならば、実際、両翼から攻める方が効率もいい!」
「だが、兵力が分散することになる」
忙(せわ)しなく言葉を交わしながらも、既にアンドレスとロレンソのそれぞれの腕は、無意識にサーベルと銃を装着し直し、砂塵や草にまみれた甲冑を手早く払って体勢を整えていく。
アンドレスは己の兵たちの方へ強い眼光を閃かせ、「即座に隊形を整えよ!」と視線で号令を送りながら、ロレンソに、今一度、向き直った。
「さっきの奴らの砲撃を見ただろう?!
あれほどの武装で固められた砦の正面突破は無理だ。
脇を狙うなら、いずれにしろ、突破口は狭い。
むしろ、兵力を分散させた方が得策だ。
さあ、急ごう!!」
「うむ…」
そう低く唸ってから、吹き止まぬ強風の中でロレンソは乱れた髪を手の平で撫でつけ、それから、「わかった」と凛々しい顔つきで頷いた。
アンドレスも笑みを返して、力強く相手の肩を握り締める。
それから、敏速な足取りで、背後に控える己の軍の方へと踵を返した。
こうしてアンドレスやロレンソの一行が再び行軍を開始した頃、敵将アレッチェは、彼もまた全身を強風に激しくなぶられてはいたが、己の配下の兵たちの無様(ぶざま)に混乱したさまに、口角から唾を飛ばしつつ激昂していた。

「馬鹿者どもめ!!
ただの一時的な疾風だ。
さっさと隊形を整えろ!!」
それから、彼は、己にぶち当たってくる石類や木片を鉄製の盾で荒々しく弾き返しながら、トゥパク・アマルの方を苛立たしげに睨(ね)めつけた。
「この場所の天候や風の性向を知っていれば、誰にでもできることだ。
このような子ども騙しまで使うとは、トゥパク・アマル、おまえも、余程、手の内が尽きてきたと見える」
そう憎々しげに言い放つアレッチェを冷ややかに見つめていたトゥパク・アマルの瞳が、再び、鋭い閃光を放つ。
そして、瞬間、トゥパク・アマルは僅かに視線を伏せて何かを口の中で唱えると、スッと、しなやかな右手を天高く振り上げた。
すると、たちまち暴風は鎮まり、上空を覆っていた暗雲も、潮が引くようにサァッと後退していくではないか。

辺りには、何事も無かったかのように、先刻までの明るい午後の陽光が燦々(さんさん)と降り注ぎはじめた。
「――…!!」
さすがに言葉を失ったまま呆然と立ち竦むアレッチェたちを涼しげな眼差しで見下ろしたまま、トゥパク・アマルは、風で乱れた前髪をいかにも優美な手つきで掻きあげた。
それから、目の端でアレッチェに一瞥をくれると、その引き締まった口元を僅かに上げて、フッと、笑みを浮かべる。
人を喰ったような――少なくともアレッチェには、そう思われた――トゥパク・アマルの態度に、アレッチェはカッと頭髪を逆立て、いきり立った眼(まなこ)で背後のスペイン兵たちを振り向いた。
そして、その腕を刃物さながらに鋭く振り回しながら、兵たちに罵声を浴びせる。
「おまえたち、何をボヤボヤしている!!
捕らえよ!!
あの謀反人を捕らえよ!!」
アレッチェの凄まじい剣幕に鞭打たれ、彼の背後に控えていた敵の騎兵たちが一斉にトゥパク・アマルを目掛けて突進する。
が、その瞬間、目にも止まらぬ速さで、トゥパク・アマルが腰の帯剣を引き抜いた。
それを合図に、いつしか断崖上の幅いっぱいに大きく広がって散開していた彼の配下のインカ兵たちが、陶器の油壺を懐から取り出し、敵軍の迫り来る方角めがけて次々と投げつけた。
と同時に、布を巻いて火をつけたオンダ(インカ時代の投石器)の石を野性の敏捷さで投げ放ち、中空に舞う無数の油壺を正確に打ち砕いていく。
草に覆われた地面には、先ほどの暴風のために、様々な武具類と共に布切れや火薬類が散乱しており、そこに砕け散って落下した多数の壷から飛び散った油が発火して、たちまち大地に炎の壁が立ちはだかった。

一瞬で先刻以上の混乱に陥った敵兵らの虚を突いて、トゥパク・アマルたちは、すかさず馬の踵を返して砦の方角から反転すると、そのまま風の如く馬を駆り立てて行く。
「おのれトゥパク・アマル、逃げる気か――!!」
みるみる小さくなっていく彼らの背に向けて、炎の向こうから、獰猛なアレッチェの怒声が響き来る。
そんなアレッチェの傍に、いきり立ったスペイン兵たちが駆け寄った。
「アレッチェ様、あの謀反人どもを追いかけます!
我々を愚弄したあの者どもを、一人残らず必ずひっ捕らえ、閣下の御前に引っ立てて参ります!!」
が、さすがにアレッチェは、「ならん!!」と、それらの今にも馬を駆り出さんばかりの兵たちを反射的に制した。
「ならん!!
深追いは無用だ!!
今は、この砦を手薄にしてはならん!!」
とはいえ、その内心では、すっかり逆上してしまった己を懸命に抑え込もうと必死であったのだが。
冷静冷徹なはずの己自身をかなぐり捨て、憎悪と興奮に呑まれるままに相手の手の内で無駄に吠え散らしていた自らに、アレッチェは耐え難い胸のムカつきを覚え、汗みどろの顔全体を手の甲で荒々しく拭い去った。
(くそ…!!
トゥパク・アマル!!
このわたしを、わざわざ焚き付けに来たのだ。
それに乗せられ、このように取り乱すなど、我ながら何と愚かしい……!)

他方、トゥパク・アマルは、味方の軍勢と共に断崖を馬で駆け下りつつ、周囲の様子に隙無い視線を走らせる。
先刻、敵方に悟られぬよう己らの背後を急いで迂回していたアンドレスたちの軍勢は、既に移動を終えているようだった。
トゥパク・アマルは、今一度、疾風の中で敵陣を振り返る。
そして、追っ手の来ぬことを視認すると、漆黒の長髪を風に吹き流したまま、静かに微笑した。
(さすがに、あの者らしく深追いはせぬか)
それから、再び決然と前方に向き直り、刃のような輪郭で閃く目元を研ぎ澄ませた。
(今はさらばだ、アレッチェ殿。
この決着は、決戦の場にて――!!)


